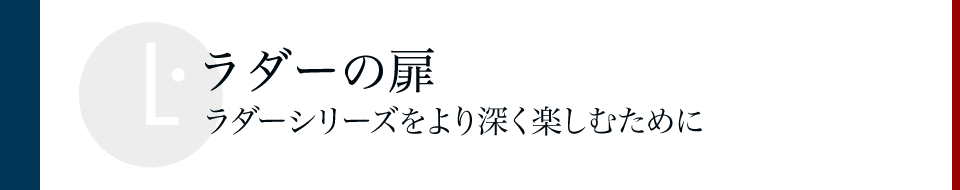
山久瀬洋二
「武士道」を読むにあたって知っておきたいこと。
それは、なぜ新渡戸稲造が英文でこうした書籍を出版しようと思ったかという動機ではないでしょうか。
新渡戸が「武士道」を書いたのは、日露戦争前夜の1900年です。
新渡戸は、南部藩の武士の子に生まれました。南部藩は幕末に新政府軍に抗い、秋田の久保田藩へ出兵します。幼少期に戊辰戦争の悲劇を目の当たりにし、誰よりも武士のあるべき姿ということを教えられ、自らも考えてきたはずです。
しかし、一方で明治時代にはいり、新渡戸は西欧文化に傾倒し、北海道でクラーク博士の足跡の残る札幌農学校でキリスト教を知り、その後欧米で学び、キリスト者となります。そしてさらに、アメリカ東海岸のメリーランド州で学んでいた頃、キリスト教の中でも特に純粋な魂の活動を説いたクエーカー教徒となったのです。
そんな新渡戸が、神と向かい合い、博愛を説きながらも、日本人としてのアイデンティティである武士道をアメリカ人に紹介した背景は何でしょうか。
迫り来るロシアの脅威に直面し、一面では内村鑑三のように戦争に反対しながらも、他面では日本人の美学を海外に紹介することで、欧米の人々の日本への好感を醸成しようとした、祖国への愛情がそこにあったのでしょうか。
その行為からは、自らの背景を理解してもらおうという、キリスト者としての率直で前向きな意思もみえてきます。
実際、「武士道」が発表されると、その流暢な英語も手伝って、アメリカ社会でたちまち話題となり、当時の大統領で日露戦争の講和にも奔走したセオドア・ルーズベルトの愛読書にもなったといわれています。
では、「武士道」は、ただ海外に日本の価値観を紹介しただけの書籍でしょうか。実は、この作品は二つの文化に挟まれた国際人の苦悶の書でもあったのです。
西欧文明と日本の伝統的な価値との融和と確執。
これは新渡戸がその後も常に悩み、苦悶した課題だったのです。
「武士道」を執筆して32年後、新渡戸は軍国主義化する日本に警鐘をならし、世論の批判に晒されます。一方で欧米においては日本人の価値観や文化を理解してもらおうと奔走しますが、それが時代に逆行し、海外の友人をも失います。
ある意味で、新渡戸稲造は日本人が国際人となったときに陥り易い狭間に引き込まれてしまいます。双方の文化への理解が深ければ深いほど、双方から孤立してしまうという矛盾を彼は抱えなければならなかったのです。悪くすると、それは楽観的な日和見主義いう誤解も与えかねません。
「武士道」は、新渡戸という国際人の先駆けが、欧米に向けてチャレンジした力作であり、同時に、日本人として西欧とかかわる人格そのものの、魂の叫びだったのです。
祖国と、新たに受け入れた文化との狭間をどう見詰め、人類共通の課題である相互理解への道を見いだすか。それは、これからも人類そのものが知恵を出し合ってゆかなければならない永遠のテーマです。
しかも、それは、海外とかかわる人々が個々に体験し、乗り越えてゆかなければならない、ある意味で極めて日常的な、それでいて深刻な問題なのです。
1933年。カナダのバンフでの国際会議に出席した新渡戸稲造は、帰国前に体を壊し、肺炎を併発し、カナダ西海岸の港町ビクトリアで永眠します。
今、ビクトリアと盛岡市はそんな縁で姉妹都市となっていますが、新渡戸の死後の日本がたどった道は、それとは裏腹なものでした。
まもなく日本は中国と出口のない戦争をはじめ、やがて太平洋戦争へと拡大していったことは周知の事実です。
新渡戸が最後に訪れたカナダでも、またキリスト教徒として生きることを決めたアメリカでも、そこに住んでいた日系人は強制収容所に送られ、新渡戸と同じように国際社会で生きる人々が、祖国と居住する国との間で苦しみました。
そして、彼の苦悩はそのまま今でも世界で活躍する多くのビジネスマンが、あるいは日中関係の悪化などで矢面に立った海外在住者が、多かれ少なかれ経験している事柄なのです。
武士道を、そうした側面を考えながら読んでみると、日本の伝統を見事に描いたセンテンスの一つ一つから、グローバルとはなにかという、世界に共通した課題を見いだすことができるはずです。
新渡戸稲造 (著者)
ロジャー・アルバーグ (リライト)
ISBN: 9784896844429
ラダーシリーズは、使用する単語を限定して、やさしい英語で書き改められた、多読・速読に最適な英文リーダーです。巻末にワードリストが付属しているため、辞書なしでどこでも読書が楽しめます。